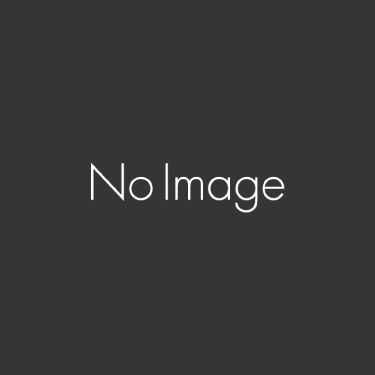先日、感覚統合療法の基礎編と応用編のオンラインセミナーを受講しました。内容はどれも興味深いものでしたが、特に印象に残ったのが「日常生活の中で感覚統合を促す仕掛けを散りばめる」という考え方です。このアプローチが、作業療法士として大切にしてきた「生活を基盤とした支援」の考え方と深くつながっていると感じました。
感覚統合を促す環境設定の具体例
セミナーでは、子どもの遊び場の環境設定について次のような例が紹介されました。
庭に設置された小さな小屋には小窓があり、子どもがその窓を通り抜けるには体を工夫して動かさなければなりません。肩や体の位置を調整しながら窓をすり抜け、さらにその先には跳ねるタイヤが設置されている。こうした仕掛けによって、子どもは自然と体の関節や筋肉を使い、多様な感覚刺激を受けることができます。
一方で、感覚過敏の子どもにとっては刺激が強すぎる場合もあります。そのようなときには、小屋の中に隠れられるスペースを設けて、一旦こもりながら感覚の沈静化を図る「逃げ場」を用意することが大切です。
日常の中で感覚を引き出す仕掛け
これらの工夫は、作業療法士としての「動き出しは本人から」という考え方と非常に近いものがあります。私たち作業療法士の役割は、リハビリの時間を充実させることだけではなく、日常生活が豊かになる仕掛けを考えることです。そのため、日常的に自然と体を使う場面を設計し、本人が無理なく体を動かせる環境を整えることが重要だと改めて感じました。
気づきを今後の実践に
今回のセミナーで学んだ「感覚統合を日常に散りばめる」という考え方は、私がこれまで実践してきた作業療法の方向性とも合致しています。感覚統合療法と「動き出しは本人から」という考え方の関連性については、また改めてお話ししたいと思います。この気づきを、今後の支援や環境設定にしっかり活かしていきたいです。
少しでも皆さんの実践のヒントになれば嬉しいです!